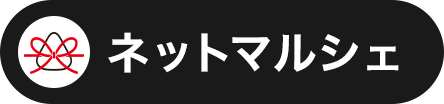12月の旬はこちら
岩国れんこん

岩国レンコンは、もっちりとした粘りとシャキシャキとした食感が特徴の高品質なれんこんです。江戸時代から栽培され、岩国藩主の吉川家にも愛された伝統野菜として知られています。温暖で日照時間が長い気候が栽培に適しているため、毎年8月から4月にかけて収穫され、特に年末年始の縁起物として重宝されています。
食べ方
岩国レンコンは煮物や天ぷら、サラダなどさまざまな料理で楽しめます。煮物にすると粘りが引き出されて濃厚な味わいを楽しめ、天ぷらではシャキシャキ感が際立ちます。スライスしてサラダに加えれば、独特の歯応えがアクセントとなり、食卓を彩ります。
選ぶポイント
皮が淡褐色で太く重みがあり、まっすぐな形のものを選びましょう。切り口が見える場合は、白くて肉厚なものが新鮮です。また、穴が小さく、黒ずんでいないものを選ぶと良いでしょう。
にんじん

にんじんの原産地は中央アジアで、日本には17世紀に東洋ニンジンが伝わり、1800年代に西洋ニンジンが導入されました。山口県では平成13年に山口市の幸崎干拓で本格的な栽培が始まり、現在では萩市平蕨台や千石台など、県内各地で栽培が進んでいます。各地域の標高差を活かし、秋から春にかけてリレー出荷を行うことで、安定した供給を実現しています。
食べ方
にんじんは生でも加熱してもおいしく、サラダやスムージー、炒め物、煮物など幅広い料理に使えます。生のままサラダにすると、甘みとシャキシャキ感が楽しめ、スムージーに加えると自然な甘さが引き立ちます。炒め物や煮物では柔らかくなり、甘みがさらに増します。色鮮やかなオレンジ色が料理に彩りを添え、食欲をそそります。
選ぶポイント
選ぶ際は、色が鮮やかでツヤがあり、表面がなめらかなものを選びましょう。青みがかったものは避けるのがポイントです。保存する際は、表面の水気をしっかり拭き取り、新聞紙に包んでビニール袋に入れ、立てて冷蔵庫で保存すると鮮度が保たれます。
アンコウ

アンコウは「鍋の王様」と称され、特に冬に旬を迎える魚です。この時期になると、肝が肥大して旨味が増し、「海のフォアグラ」とも呼ばれる贅沢な味わいを楽しむことができます。アンコウは海底の砂泥質に生息し、頭の上にある釣り竿のような器官で餌を引き寄せ、一気に捕食するユニークな習性があります。山口県の下関漁港はアンコウの水揚げ量が日本一で、地域を挙げてアンコウの消費拡大と観光促進に力を入れています。
食べ方
アンコウは、全身が食べられる「海の七変化」とも呼ばれます。主に鍋料理として楽しむことが多く、特に「どぶ汁」と呼ばれるアンコウの肝を使った濃厚な鍋が有名です。その他、刺身や唐揚げ、煮物としても絶品です。コラーゲン豊富な皮やゼラチン質が豊かで、美容や健康にも良いとされています。刺身には独特の食感があり、鍋では旨味がスープに染み出し、極上の味わいが楽しめます。
選ぶポイント
アンコウは調理が難しいため、スーパーなどではパックに入った調理済みの状態で販売されることが多いです。新鮮さを見分けるには、ドリップ(液汁)が少ないものを選ぶのがポイントです。ドリップが少ないほど、鮮度が保たれており、アンコウ本来の旨味を楽しむことができます。
ヒラメ

ヒラメは、真鯛と並ぶ白身魚の代表で、淡泊な肉質が特徴です。カレイに似ていますが、「左ヒラメの右カレイ」といわれるように、腹側を下に向けたときに目が左側にあるのが特徴です。ヒラメは砂泥質を好み、魚類を捕食して生息しています。ヒレの付け根の「縁側(えんがわ)」はコラーゲンを含み、コリコリとした歯ごたえがあり、刺身や寿司に使われることが多い部位です。山口県では、主に底引き網漁業や刺し網漁業で漁獲されており、下松市や長門市では養殖も行われています。
食べ方
ヒラメの刺身や昆布じめは、淡白な味わいを引き立てるためにおすすめです。縁側はコリコリとした食感が楽しめます。また、あらや骨の部分は唐揚げにすると美味しくいただけます。
選ぶポイント
体に張りがあり光沢があるもの、うろこがしっかりついていて、裏側の白い部分が赤く充血していないものを選びましょう。